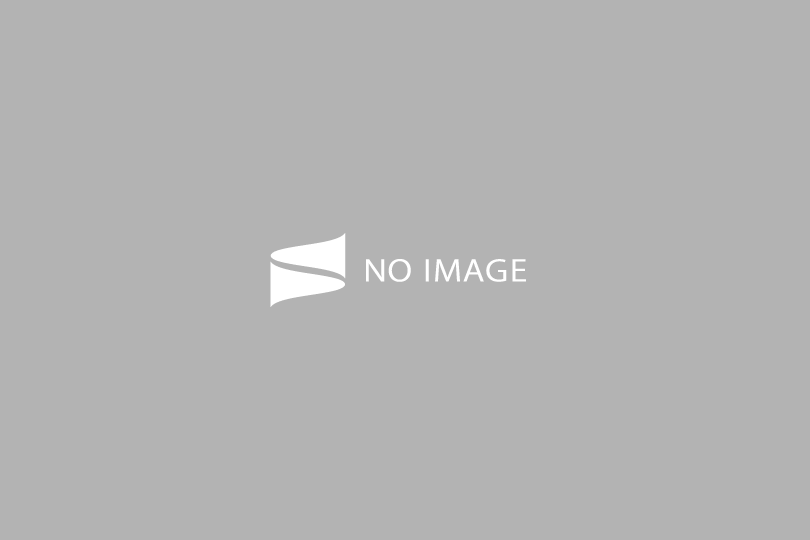人生の終末期に向けて、より良い人生を送るための準備活動である「終活」。
具体的には、医療や介護についての意思表示・身の回りの整理・葬儀やお墓の準備などが含まれます。
終活は、残された家族の負担を軽減するだけでなく、自身の人生をより豊かにするための前向きな活動です。
今回の記事では、終活とはどのようなものなのかだけでなく、メリットややっておくべきことなどを紹介します。
「これから終活を始めたい」「家族の終活をサポートしたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
終活を行う理由と必要性
かつては家族や地域社会で支え合っていましたが、現代社会では少子高齢化や核家族化が進み、老後や死後の準備について個人で備える必要性が高まりました。
また平均寿命の伸長による介護や相続に起因するトラブルも、終活の必要性が高まっている要因の一つです。
大切な方同士のトラブルを未然に防ぐためにも、終活は重要な役割を果たします。
また終活は、人生の終わりを考えるだけでなく、残りの人生をより良く生きるための活動です。
自分の価値観や希望を明確にして積極的に行動することで、充実した毎日を送ることが可能になります。
終活は後ろ向きなものではなく、前向きな活動であることを理解したうえで進めることが大切だと言えるでしょう。
終活のメリット
終活を行うことには、多くのメリットがあります。
- 家族の負担軽減:葬儀やお墓・相続に関する希望を事前に伝えておくことで、残された家族の負担を大幅に軽減できます。特に葬儀は短期間で多くのことを決めなければならず、家族の精神的な負担も大きいため、事前の準備が重要です。
- 相続トラブルの回避:遺言書を作成し財産分与について明確にしておくことで、家族間の相続トラブルを未然に防ぐことができます。
- 自分らしい人生の実現:終活を通して自身の価値観や人生を振り返ることにより、残りの人生をどのように生きたいか、より具体的に考えることができます。
- 死への不安の軽減:死後の準備を進めることで、死に対する漠然とした不安を解消し、前向きな気持ちで残りの人生を過ごせるようになります。
終活を始めるタイミング
終活を始める年齢に、明確な決まりはありません。
しかし一般的には、60代後半から70代にかけて始める方がほとんどです。
この時期は定年退職や子供の独立など、ライフスタイルが大きく変化するタイミングでもあり、体力や判断力も比較的安定しているため、終活を始めるのに適していると言えます。
ただし、健康状態に不安を感じ始めたら、40代や50代であっても早めに動き出すことが大切です。
万が一に備え、少しずつ進めておくことが安心へのカギと言えるでしょう。
終活でやっておくべきことリスト
終活でやるべきことは多岐に渡りますが、主な項目は以下の通りです。
身辺整理
不要なものを処分し、身の回りを整理しておきましょう。
遺品整理は、家族にとって時間的にも経済的にも大きな負担となるため、元気なうちに整理しておくことが重要です。
またあらかじめ処分を進めておくことで、健康に不安が生じても暮らしやすい環境づくりを実現しやすくなるでしょう。
エンディングノート作成
自分の情報や希望、家族へのメッセージなどを記録します。
エンディングノートに法的な効力はありませんが、家族に大切な情報を伝えるための重要なツールです。
資産整理
預貯金・クレジットカード・有価証券・保険などを整理し、一覧表を作成しておきましょう。
その際、不要な口座は解約し、合わせて必要な情報もまとめておきましょう。
遺言書作成
相続に関するトラブルを避けるため、法的に有効な遺言書を作成します。
作成した内容に不備があると無効となるケースもあるため、専門家への相談も検討しましょう。
葬儀・お墓の準備
葬儀の形式や参列者リスト、お墓の種類などを検討し、希望をまとめておきましょう。
手続きや事前の話し合いが必要な場合もあるため、合わせて進めておくと安心です。
デジタルデータの整理
パソコンやスマートフォンのデータ・SNSアカウントなどを整理します。
IDやパスワードは一覧にまとめ、不要なデータは削除しておきましょう。
各種サービスの見直し
生命保険や医療保険について、不要な契約を解約したり内容を見直したりしましょう。
年齢やタイミングによって必要なプランは異なるため、特約や保険の対象範囲なども合わせて確認しておくと安心です。
医療・介護の意思表示
延命治療の希望や介護が必要になった場合の希望など、万が一の場合について家族と共有しておきましょう。
合わせて複数の介護サービス提供者について調べておくと、選択の幅が広がります。
緊急連絡先の共有
かかりつけの病院・介護施設などの連絡先は、必ず家族に伝えておきましょう。
またわかりやすい場所で管理し、緊急時のトラブルを回避できるようにしておくことも重要です。
老後資金計画
年金・貯蓄・生活費などを確認し、老後の資金計画を立てましょう。
あらためて確認しておくことで、その後の生活設計に役立ちます。
やりたいことリスト作成
資金計画をもとに、残りの人生でやりたいことをリストアップし、積極的に行動しましょう。
家族や友人との思い出づくりも、終活において重要な要素です。
不動産問題の解決
不動産の売却や相続・生前贈与などを検討し、必要な手続きを行いましょう。
遺言書での相続先の指定はもちろん、手続きが煩雑であったり処分が難しい不動産に関しては専門家へ相談し、相続する方の負担とならないようにしておくことも重要です。
エンディングノートの書き方
エンディングノート自体に法的拘束力はないものの、亡くなった方の意思を確認でき、思い出を共有できるツールともなるため、作成しておくことをおすすめします。
作成する際は、以下の項目を記載すると良いでしょう。
- 自分史: 生い立ちから現在までの歴史や学歴・職歴・思い出の場所・趣味などを記録します。
- 家族情報: 万が一の時に知らせてほしい親戚や、友人・知人の連絡先などを記載します。
- 医療情報: かかりつけの病院名や病歴・持病をはじめ、服用している薬などを記載します。
- 保険情報: 保険会社名・契約プラン・契約者名や保険金受取人などを記載します。
- 財産情報: 所有する預貯金や不動産・株式や投資信託・貴金属などを記載します。
- 介護の希望: 入居したい施設や具体的な介護方針などを記載します。
- 葬儀の希望: 希望する葬儀の内容や納骨の方法、喪主に関してなどを記載します。
- 遺品の扱い: 趣味のコレクションや思い出の品などについて、どのようにしてほしいかを記載します。
- デジタル情報: スマートフォンやインターネットのIDやパスワード・メールアドレスなどを記載します。
- 家族や友人へのメッセージ: お礼や感謝の気持ち、伝えたいことを自由に記載します。
エンディングノートは一度に全てを書ききろうとせず、時間をかけて少しずつ書き進めましょう。
また個人情報の管理には十分注意し、保管場所を家族に伝えておくことが大切です。
遺言書の種類と作成方法
法的な手続きや届け出が必要なものに関しては、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書には、主に以下のような3つの種類があります。
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で全文を書き、日付・署名・押印をする必要があります。財産目録はパソコンで作成も可能です。
- 公正証書遺言:公証人に作成を依頼する遺言書です。公証人が作成するため法的に有効であり、内容の正確性が保証されます。
- 秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書を作成できます。ただし、法的な要件を満たさないと無効になる可能性があるため、作成には注意が必要です。
どの遺言書を作成する場合でも、法的な要件をしっかりと満たす必要があるため、専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをおすすめします。
老後の住まいに関する計画
老後の住まいについても、計画を立てておきましょう。
自宅で最期を迎えるか施設への入居をするかによって、老後資金の計画も大きく変わるため、家族や近しい人と話し合って対応を決めておくことが大切です、
- 自宅での生活継続:自宅で過ごす場合は、バリアフリー化やリフォームを検討し、快適かつ事故を回避できる住まいづくりを行いましょう。
- 施設への入居:介護施設の情報を集め、見学に行きましょう。これまでの生活や老後の資金を算出し、無理のないサービスを提供する施設への入居を進めることが大切です。
- 家族との同居:転居先での生活が大きく変化することも少なくないため、同居する家族とよく話し合って準備を進めましょう。
介護や入院・転居が必要になった場合も考慮し、早めに計画を立てておくことが重要です。
葬儀準備のポイント
終活で重要な項目の一つが、葬儀に関する意思表示です。
ご自身の最期の希望を叶える場でもあるため、詳細に記載しておきましょう。
葬儀の準備では、以下の点を検討しましょう。
- 葬儀形式:どのような形式の葬儀を希望するかを決めます。家族葬や一般葬をはじめ、宗派や日取りなども記載しておきましょう。
- 参列者リスト:誰に葬儀に参列してほしいか、リストを作成します。
- 遺影:どのような写真を使用するか、事前に準備しておきましょう。
- 生前契約:生前に葬儀社と契約しておくことで、よりスムーズに対応してもらえるでしょう。
- 生前葬:生きている間に葬儀を行うこともでき、直接顔を合わせてお別れを伝えたい方に選択されています。
これらの点を具体的に決めておくことで、家族の負担を減らすことができます。
お墓の種類と選び方
葬儀と同様に、お墓についても希望を伝えておきましょう。
お墓には、以下のような種類があります。
- 公営墓地:自治体が運営する墓地で、費用は比較的安い傾向がありますが、利用に条件があります。
- 民営墓地:公益法人や宗教法人などが運営する墓地で、宗派を問わず利用できることが多いです。
- 寺院墓地:お寺が運営する墓地で、檀家になる必要がある場合がほとんどです。
- 永代供養墓:霊園や墓地の管理者が永続的に管理するお墓で、継承者がいない場合や墓じまいを行った方にも適しています。
お墓を選ぶ際には、立地や設備・費用などを考慮し、家族と相談して決めることが大切です。
またどのように管理して行くかや、いつまで供養を続けるかについても決めておくと、のちのトラブルを防げます。
デジタル終活の重要性
近年はSNSやサブスクリプション型の契約を行っている方も多く、契約された方の死後にログインIDやパスワードがわからず、解約できない事例も相次いでいます。
そのため、デジタル終活についてもこれまでの終活と同様に進めておくことが望ましいでしょう。
デジタル終活では、以下の点に注意が必要です。
- デジタルデータの整理:パソコンやスマートフォンに保存されている写真や動画などのデータを整理します。不要なデータは削除し、必要なデータはバックアップしておきましょう。
- SNSアカウントの整理:さまざまなSNSアカウントを整理します。パスワードを家族に伝えておくか、アカウントの削除を検討しましょう。
- ID・パスワードの管理:ウェブサイトやサービスのID・パスワードをリスト化し、家族が確認できるようにしておきましょう。
- サブスクリプションサービスの解約:不要なサブスクリプションサービスを解約しましょう。定期的に契約内容を確認し、必要に応じて随時解約を進めておくことをおすすめします。
デジタルデータは個人的な側面から家族が把握しにくいため、事前に整理しておくことが大切です。
老後の生活を支える契約の検討
年齢によって、生活に必要なものは異なります。
特に定年退職後や後期高齢者となる前に、考えておくべきものも少なくありません。
老後の生活を支える契約には、以下のようなものがあります。
- 財産管理委任契約:自分の財産の管理を代理人に委任する契約です。
- 任意後見契約:認知症や事故などで判断能力が低下した場合に、財産管理や生活に必要な手続きを後見人に委任する契約です。
- 見守り契約:任意後見契約の開始時期を支援者に判断してもらう契約です。
- 死後事務委任契約::死亡後の事務手続きを第三者に委任する契約です。家族がいない場合や、疎遠となっている場合に有効です。
- 民事信託:自分の財産を家族や親族に託し、管理・運用・処分してもらう契約です。
- ペット関連契約:ペットの世話を条件に財産を贈与する契約や、ペット信託などがあります。
これらの契約には複雑なものも含まれるため、専門家(弁護士や司法書士)に相談しながら、慎重に検討しましょう。
また家族にも契約内容を確認しておくと、もしもの際のトラブルや混乱を回避できます。
終活に必要な資金の準備
終活には、ある程度の費用がかかります。
以下の方法で資金を準備しましょう。
- 貯蓄:普段から日々の生活費を節約し、貯蓄を増やしましょう。ただし死後は口座が凍結される場合もあるため、対策をしておく必要があります。
- 節約:必要のない通信費や保険料・光熱費など、固定費を見直しましょう。見直し自体が終活につながる場合もあります。
- 資産の売却:不要な不動産や貴金属などを売却し、現金化しましょう。現金化することで、評価の差によるトラブルを防げます。
- 投資:できる限り早い段階から投資することが大切ですが、リスクについてもきちんと把握したうえで行うことが大切です。
老後の資金準備については、専門家(ファイナンシャルプランナー)に相談することも検討しましょう。
専門家の立場から、現在の状況を加味して最善の選択ができるようアドバイスしてもらえます。
終活に関する専門家への相談も検討しよう
終活を進めるうえで、専門家の力を借りることも検討しましょう。
特に契約やリスクを伴う投資を行う場合は、専門家によるチェックが重要です。
- 弁護士:遺言書の作成や相続トラブルの解決など、法律に関する相談ができます。
- 司法書士:相続手続きや不動産登記など、法律に関する手続きを依頼できます。
- 税理士:相続税対策や各種税金に関する相談ができます。
- ファイナンシャルプランナー:老後資金計画や資産運用・終活費用の準備に関する相談ができます。
- 介護施設:介護施設に関する相談や見学のサポートを受けられます。特に専門的なケアを受けながら終活を進めたい方は、積極的に相談しましょう。
専門家はそれぞれの分野の知識や経験を持っているため、的確なアドバイスやサポートを受けることができます。
終活の注意点
終活は、自身の死に向き合う時間となる場合も多いため、ストレスを感じることもあります。
一人で抱え込まず、家族や信頼できる人に相談しましょう。
また、以下の点に注意が必要です。
事前の情報共有
終活で作成したエンディングノートや遺言書・葬儀やお墓の計画などは、自分だけで完結せず家族や信頼できる人に情報を共有しておきましょう。
家族がその存在を知らない場合、せっかくの準備が活かされない可能性があります。
特に遺言書や契約書類は、保管場所や内容を明確に伝えておくことが重要です。
また、記載する内容についても事前に家族と話し合うことで、誤解やトラブルを防ぐことにつながります。
デジタル終活は早いうちから
インターネットやスマートフォンの普及により、デジタル遺産の整理が必要な時代になっています。
メールやSNSのアカウント情報・ネットバンキング・クラウドサービスなどは、適切に管理しておかないと家族に負担をかける可能性があります。
各アカウントのIDやパスワード・削除の指示などを整理し、信頼できる家族や専門家に伝える方法を検討しましょう。
特にサブスクリプション契約のものについては、早めに解約・変更を進めておくと、不要な費用や手間を抑えられます。
焦らない
終活は、一度にすべてを終わらせる必要はありません。
年齢や状況に応じて、優先順位をつけながら少しずつ進めることが大切です。
焦るあまり、不完全な内容や誤った情報を家族に残してしまうと、かえってトラブルの原因になる場合もあります。
無理なく、自分のペースで進めることを心がけましょう。
早めに進めたい、また専門的な内容を確認しながら行いたい場合は、専門家へ相談することも検討しましょう。
まとめ
終活とは、人生の最終段階をより自分らしく生きるために行う準備活動です。
その理由として、家族への負担軽減や、自身の希望を叶えるための計画が挙げられます。
終活を行うことで自分の意思を明確にし、安心感を得られるメリットがあります。
始めるタイミングとしては、健康で考える余裕があるときが最適です。
また取り組むべきことは多岐にわたり、エンディングノートの作成や遺言書の準備、住まいや葬儀、お墓の計画、さらにはデジタル資産の整理などが含まれます。
さらに老後の生活を支える契約や必要な資金の計画も重要です。
こうした準備を進める際には、法律や金融の専門家への相談が役立ちます。
ただし、終活は自身の価値観や家族との対話を大切に進める必要があります。
一度に全てを完了する必要はなく、注意点を把握しながら、少しずつ取り組むことが理想的です。
終活を通じて、安心して老後を迎え、人生の最終章を充実させましょう。
東京都で終活のことならこちら
関東で終活のことならこちら
関西で終活のことならこちら
東海で終活のことならこちら
四国で終活のことならこちら
東北で終活のことならこちら
九州で終活のことならこちら